1. 市場の回復と経営のポイント
新型コロナウイルス禍によって冷え込んだ飲食市場は、2024年から2025年にかけて急速に回復しつつあり、売上高はパンデミック前の水準に戻りつつある。特にファストフードや居酒屋、ラーメン・焼肉店など高回転もしくは高単価の業態が成長を牽引している。成功している店舗は、①回転率を高めたり客単価を上げる工夫、②食材費・人件費・家賃などのコスト最適化、③コンセプトと立地・顧客層の適合という三つの要素を重視している。これから出店を検討する場合、これらの点を意識して経営計画を立てることが重要である。
2. 2025年の食トレンド
2025年の飲食トレンドは「伝統×革新」「懐かしさ×新しさ」をテーマに多様化が進んでいる。
- 発酵食品の進化: 健康志向の高まりにより、腸内環境改善やダイエット目的で発酵食品が注目を集めている。味噌を使ったヴィーガンレシピや低糖質メニュー、ドレッシングなど新しい用途が広がっている。
- ヨーグルトの多様化: ギリシャヨーグルトを使ったボウルや、乳酸菌・プレバイオティクスを強化した機能性ヨーグルト、植物性ヨーグルトなど、健康志向かつヴィーガン対応の商品が増えている。
- レトロフードの復活: 昭和や2000年代初頭の料理やスイーツが再解釈され、ナポリタンやクリームソーダ、キャロットケーキなどが再び注目されている。ノスタルジーと新奇性の組み合わせがSNS映えし、若年層にも人気である。
- ハーブとスパイスの再評価: シソやヨモギ、山椒など日本の薬味を使ったノンアルコールカクテルや、ルッコラをスーパーフードと位置付けたサラダ、コリアンダーやバジルを使ったアジアン風料理など、ハーブやスパイスの用途が広がっている。
- アジア料理の多様化: 台湾のタロイモスイーツや飲料、韓国の発酵スープ(清麴醤チゲ)やハーブサムギョプサル、ベトナムの蒸し春巻きやライスペーパー料理など、アジア各地の料理が健康的で手軽な食事として人気を集めている。
こうしたトレンドはSNS映えするビジュアルや健康志向、多様性を重視しており、店舗メニューや開発方針のヒントになる。
3. 法制の最新情報
2025年6月1日から、職場における熱中症予防措置が義務化される。これは近年、熱中症による労働災害が増加していることを受けて労働安全衛生規則が改正されたもので、事業者には次の三つの義務が課される。
- 早期発見体制の構築: 作業中の体調変化を報告するルールや、温度・湿度の監視、WBGT値(暑さ指数)に応じた注意喚起などを整備する。
- 緊急対応手順の策定: 冷却方法、救急搬送の手順、救急連絡先を明記したマニュアルを作成し、職場全体で共有する。
- 教育と訓練の実施: 従業員に熱中症の兆候や応急処置について理解させ、定期的な研修を行う。
この規則はWBGTが28℃以上、または気温31℃以上の環境で一定時間作業する場合に適用され、厨房のような高温環境を持つ飲食店も対象となる。違反した場合は6か月以下の懲役または50万円以下の罰金が科される。飲食店では、厨房の換気改善や休憩時間の管理、通気性の良い制服や塩分・水分の摂取指導など実践的な対策が求められる。
4. まとめ
飲食業界はパンデミックからの回復が進み、健康志向やノスタルジー、アジア料理ブームなど多彩なトレンドが同時に進行している。経営者は、自店舗のコンセプトや顧客層に合わせてこれらの潮流を取り入れ、回転率や客単価の向上、コスト最適化に努めるべきである。法制面では、熱中症予防義務化など安全衛生に関する規制強化が進んでおり、法令遵守と従業員の健康管理が今後の経営課題となる。トレンドと法制の両面から情報を収集し、変化に柔軟に対応することで、持続的な成長を実現できるだろう。


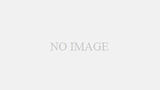
コメント